前回の記事では初音ミクを使って「せ」を変化させながら、子音の S → CH → SH → T → P のつながりを見ました。
今回は「おせんべぇ」全体の周波数特性グラフを比較してみます。
初音ミクで「おせんべぇ」は「お せ ん_m0 べ え」
通常は「おせんべい」ですが、この記事では発音にあわせて「おせんべぇ」と表記しています。
また、初音ミクで発音するにあたっては「ん」を無音化するために「ん_m0」としました。
そして「せ」の子音部分をギュッと短くして「おてんべぇ」らしく聞こえるようにしました。
全体としてどうしても「おせんべぇ」と聞こえてしまうのは、初音ミクの優秀さ、または人間の補完力の素晴らしさということにしておきましょう(笑)。
そしてこちらが、何も細工をせずに「おてんべぇ」と発音したものです。
余談ですが、上の音を聞いた後だと「おぺんぺぇ」と聞こえるという人もいました。
やはり S → CH → SH → T → P の繋がりの影響と言えそうです。
こちらが「おぺんぺぇ」です。
語尾も「ぺ」に変更してみました。
「おせんべぇ」「おてんべぇ」の周波数特性を比較
並べてみたとき、この赤囲み部分が「S」と「T」の違いということになります。
「子音を圧縮した『おせんべぇ』」と「おてんべぇ」がとても似ています。
なるほどこれなら「おてんべぇ」と聞こえるのも分かります。
そして「おぺんぺぇ」は、さらに子音が短くなっています。
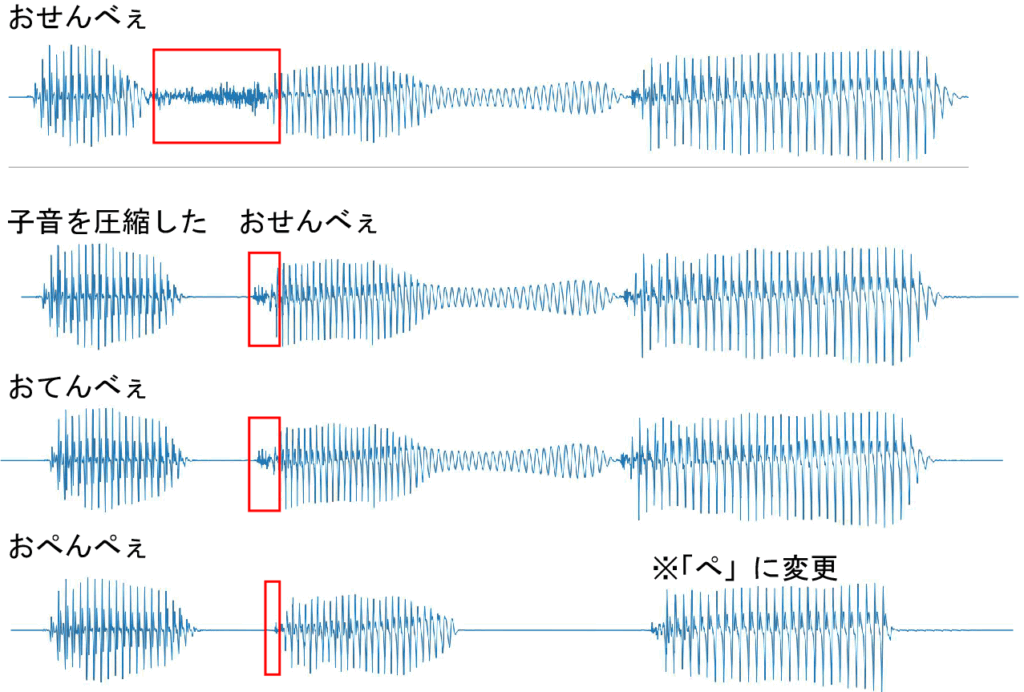
以上のことから、「さ行」はかなり長い子音であることが分かります。
十分な肺活量がないと発話できなさそうなさそうで、「さ行」が成長段階の最後になるのも分かる気がします。
まとめ
前回は「せ」の音について、子音が短くなるにつれ S → CH → SH → T → P と変化をする様子を作ってみました。
今回は「おせんべぇ」「子音を短くした『おせんべぇ』」「おてんべぇ」のグラフで類似点と相違点を比較してみました。
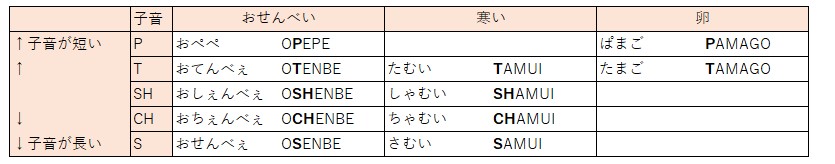
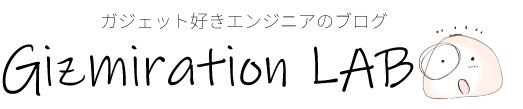
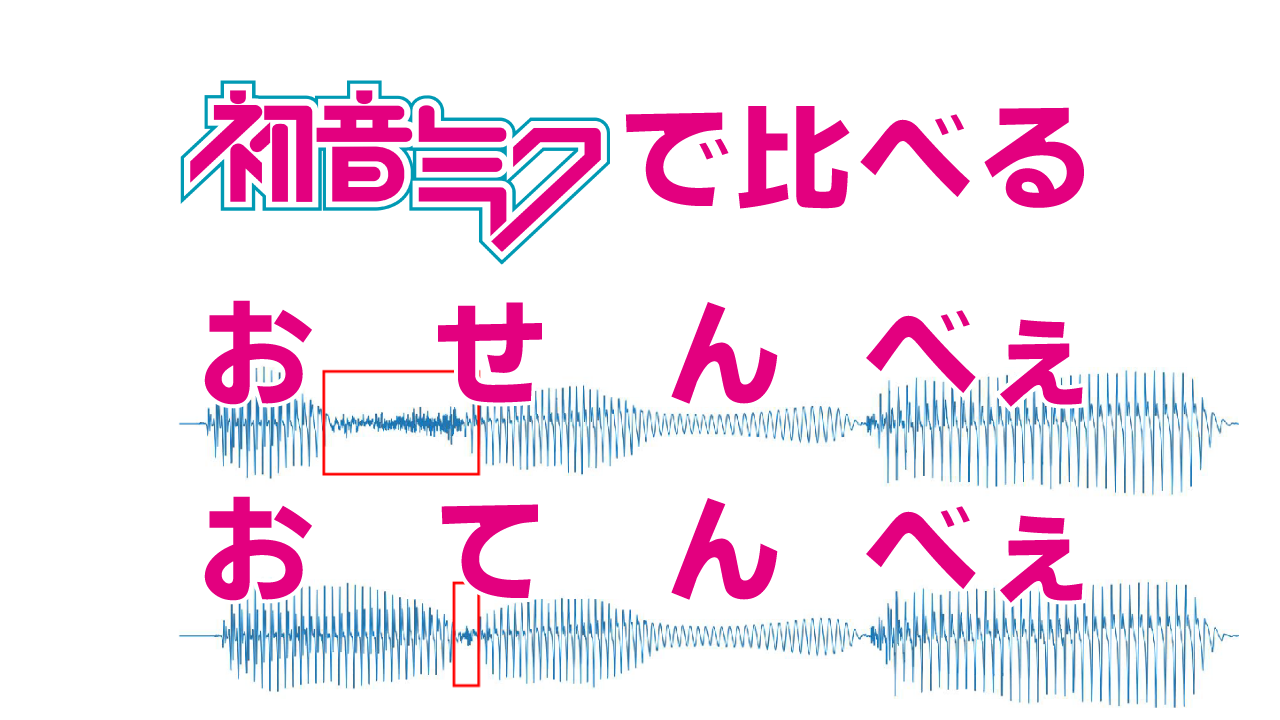
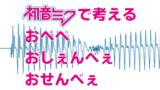
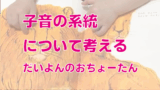
コメント