パソコンのCドライブとは?なぜC?
ドライブというのは記憶装置のことです。結論から言えば、AドライブとBドライブの次だからCドライブというわけです。以下、その経緯を解説します。
AとBの次だからCドライブ
結論から言ってしまえば、これにつきます。「AとBの次だからCドライブ」
ハードディスクやSSDが普及する遥か前、まだWindowsでもないころのこと。NECの8bitマイコンが主流だった当時、作成したプログラムの記憶媒体はカセットテープでした。後になってカセットテープより遥かに扱いやすい記憶媒体が登場しました。フロッピーディスクです。
フロッピーディスクはAドライブ
フロッピーにOSを保存しておき、ロードしてから使うという仕組みでした。このフロッピー読み取り装置にAドライブ、Bドライブと名付けられました。ちょうどWindowsが登場したころには、フロッピーよりも高速で大容量なハードディスクの金額も下がっており、ハードディスクにOSを入れるようになりました。AドライブとBドライブの次だからCドライブと名付けられた訳です。
こうなるとフロッピーを2つ持っておく必要性も下がり、Aドライブのみになりました。
Windowsが破損したりハードディスクが破損した時には、フロッピーをAドライブに挿して電源を入れると、フロッピーからDOSを起動してデータの救出などができました。
次は当然Dドライブ
その後CDドライブやDVDドライブが登場すると今度はDドライブが登場しました。
そしてUSBメモリなど外付けの記憶装置を認識するたびにEドライブ、Fドライブ、などと次の名前が付けられていきます。ちょっと例外的なのがGoogleドライブ。いきなりGドライブになりますが、これは”G”oogleドライブにちなんでのものです。
Cドライブがなくてもパソコンは起動できる
ハードディスクやSSDは補助記憶装置 なくても起動できる
この経緯から分かるのは、Aドライブ、Bドライブなどと名付けられたものたちは全てOSをロードするための”補助”記憶装置です。
AドライブのFDDから読み込んでも、CドライブのHDDからでも、DドライブのCDから、EドライブのUSBメモリなどなど、どこから読み込んでもOKです。一度ロードできたら補助記憶装置は無くてもパソコンは動きます。最近のパソコンは故障時のリカバーに使うデータをDドライブやEドライブとして備えていることも多いようです。
メモリは主記憶装置 これがないと起動はできない
メモリにロードしたプログラムを実行するという仕組み上、メモリなしにはプログラムをロードできず動きません。
パソコンを自作したことがある人は一度くらい経験があるのではないでしょうか。メモリがちゃんと挿さっていないと起動できないのはそのためです。
BIOSで起動順位を変更できる
Windows95から98くらいの時代には、フロッピーを入れたままシャットダウンし、次回起動しようとしたら「システムが見つかりません」的なメッセージを吐いて起動しない、というのもよくありました。
まとめ
AドライブとBドライブがあり、その次に登場したのでCドライブ
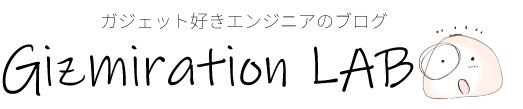

コメント